放射線治療科の最新トピックス
放射線治療科 辻野佳世子医師 インタビュー
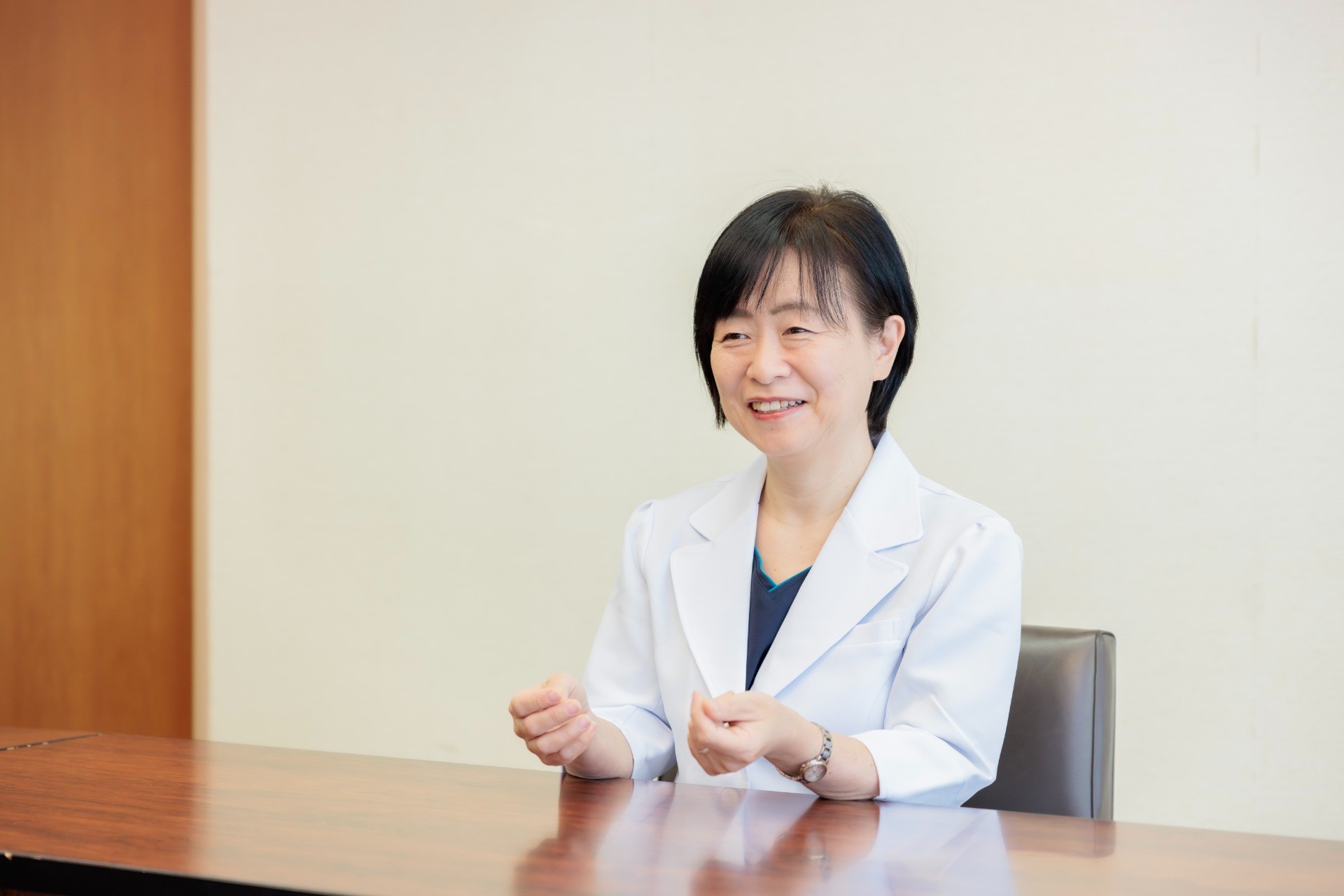
今回のインタビューでは、「切らずに治す」をモットーに、臓器温存治療として力を入れている放射線治療科診療の最近の状況について、放射線治療科 辻野佳世子医師にお話を伺いました。
まず、診療実績についてお聞かせください。
当科ではほぼ全臓器にわたるがんの治療を行います。身体の負担が小さい局所治療、手術に代わる治療として、局所進行がんの臓器を残して腫瘍を根治させる化学放射線療法が大きな柱です。手術や抗がん剤が適応にならない高齢の患者さんにも治療可能です。乳がん、婦人科がん、肺がん、頭頸部がん、前立腺がんなど臓器を残して治療する部位が多くを占めます。
コロナの影響はあったのでしょうか?
新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、がん治療の現場にも大きな影響を与えました。症状があっても受診を控えたり、がん検診を先延ばしにすることによって、初診時にすでにがんが進行している患者さんが増加しています。院内感染対策としての入院中の外出制限や面会制限の影響から多くの治療が入院から外来へ移行してきています。大きくて切除できないがんを抗がん剤との併用療法(化学放射線療法)で治癒させること、またご自宅からの通院で生活環境を変えずに治療できることは放射線治療の最大の強みです。外からX線を照射してがんを消失させる放射線治療は、体への負担が小さく免疫機能の低下はほとんどありません。仮に治療中に患者さんが新型コロナにかかったとしても、放射線治療であれば感染対策を行ったうえで治療を継続できます。
当科では機器の入れ替えがあった2019年度を除いて治療数は年々増加しています。2023年度も810人の患者さんを治療しました。コロナ禍にあっても治療数はむしろ増加し、アフターコロナもその傾向は続いています。強度変調放射線治療 (IMRT)や体幹部定位放射線治療(SBRT)など高精度治療の拡大に取り組んでおり、2023年度は全体の54%を占めるまでになりました。
最近の診療内容はいかがでしょうか?
短期照射(寡分割照射)の適応が拡大しています。コロナ渦はがんの治療法選択において、手術から放射線治療へのシフトを進めました。さらにコロナ禍によって、放射線治療自体にも期間を短縮する動きが一気に進みました。乳がん術後で5週間の治療期間を3週間に、前立腺がんで8週間を4週間に短縮する試みは、多くの臨床試験を経て現在の標準治療となっています。コロナ禍においてはがんを治すことと同時に、通院回数を減らして感染機会を減らすことも求められました。「同等の効果であれば治療期間を短縮させる」ことが我々の大命題となり、症状緩和の治療など多くで短期照射が採用されました。痛みのある骨転移に対しては1回のみ照射することがほとんどになっています。治療期間の短縮は患者さんの日常生活への負荷が減りますし、早く次の治療に取りかかれるメリットもあります。短期照射の推進が、アフターコロナの日常になりつつあります。短期照射の別の呼び方を寡分割照射と言います。定位放射線治療は超寡分割照射の代表であり、3~5回程度の照射で小さな腫瘍を消失させます。手術に代わる根治治療として引き続き、積極的に活用していきたいと考えています。
婦人科がんに対する最先端の画像誘導ハイブリット小線源治療について、詳しく教えてください。
「切らずに治す放射線治療」の代表ともいえる、子宮頸がんや腟がんに対する治療では、外照射と小線源治療を組み合わせて行うことが必須です。いずれの照射方法も、腫瘍の形状や臓器の位置関係に応じた個別のオーダーメイド治療が望まれますが、小線源治療は体内・腫瘍内に器具を挿入して行うため、医療チーム側の経験や技術を要します。従来の腔内照射は、定型の器具(アプリケータ)を子宮や腟内に挿入し、腫瘍の形状や臓器の位置関係を確認して1回高線量を照射することで良好な効果が得られます。しかし腫瘍サイズが大きい場合や、不整形の場合には、腫瘍の辺縁まで十分照射出来なくなったりします。
この問題を解決するために、当院では2016年からハイブリッド照射(組織内照射併用腔内照射)を開始しました。この治療ではアプリケータに加えて、線量が不足する組織内に針を刺入し、その中から照射することで、正常臓器を避けながら腫瘍の形状に合わせて十分な線量を照射することが可能となります。従来よりも副作用を減らし治療効果を高める研究成果が報告されており、当院の経験でも良好な成績が得られていることを英文学術誌に報告しています。このような最先端の小線源治療を、麻酔科医や高度治療室看護師の協力も得て、苦痛や不安を最小限に抑えて提供しております。
辻野医師、ありがとうございました。

